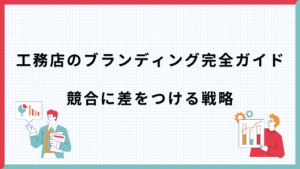【解説】住宅業界のルームツアー動画で問い合わせを獲得する方法を教えます! – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=xL9t_hddbJc
「住宅業界のYoutube 運用の教科書」を無料でダウンロード!
\ こんな方におすすめです! /
・ルームツアー動画が集客に繋がらない
・Youtubeを試したがやり方があってるか分からない
・クリック率や再生時間の目安を知りたい
・0からYoutube活用を学びたい
住宅業界でも定番となりつつある「ルームツアー動画」。
特に工務店にとっては、自社の強みや施工力、スタッフの人柄までも視覚的に伝えられる強力なブランディングツールです。
しかし、「なかなか再生回数が伸びない」「問い合わせにつながらない」といった悩みを抱える方も多いのが現実。
そこで本記事では、YouTubeルームツアーを伸ばすための具体的な工夫と、集客や問い合わせにつなげる導線設計について、事例も交えながらわかりやすく解説します。
>>住宅業界・工務店のSNS活用・YouTube運営のお問合せはこちら
なぜ今、工務店にとってYouTube活用が“不可欠”なのか?
YouTubeは世界で最も利用されている動画プラットフォームであり、毎日数十億人がアクセスしています。
住宅業界でも、2020年以降はYouTubeを活用したブランディングや集客が一般化し、動画を通じて「会社の雰囲気」や「スタッフの人柄」を伝えることが当たり前になってきました。
視聴者が住宅会社を選ぶ理由の多くは、「担当者との相性が良さそう」「この会社、なんだか好き」といった感情的な要素です。
つまり、誰が出演するか、どんな雰囲気で語られるかが、視聴者の判断を大きく左右します。
そのため出演者は、単に説明できる人ではなく、会社のこだわりや家づくりへの思いを“語れる”人が理想です。
営業担当や設計士、経営者など、現場と会社の「想い」を知る人が最適です。
逆に、知識や経験の浅い新入社員を出演させると、説得力に欠けてしまうため注意が必要です。
「出るのが恥ずかしい」と感じるスタッフがいる場合は、あらかじめ質問を用意する・構成を伝えるなど、出演者の負担を減らす工夫をしましょう。
今や、YouTubeを活用しないこと自体が機会損失につながりかねない時代です。
広報ツールとしてチラシよりも広く深く届くYouTubeは、“見つけてもらう工務店”から“選ばれる工務店”へと進化する鍵となります。
ルームツアー動画がもたらす3つの大きなメリット

ルームツアー動画は単なる映像ではなく、住宅の魅力を伝え、会社の資産となり、顧客接点を拡げる強力なマーケティングツールです。ここでは、その具体的なメリットを3つに整理して解説します。
①住宅の魅力を直感的に伝えられる
ルームツアー動画最大の強みは、住宅の魅力を“感覚的”に伝えられる点です。
広さ・質感・空気感といった、活字や静止画では伝わりにくい情報を、動画ではリアルに届けられます。
たとえば、
• 吹き抜けの開放感
• 木の素材感や光の入り方
• 実際の動線のスムーズさ
といった要素は、動画でこそ伝わる価値です。
視聴者が「この家で暮らすイメージ」を自然に持ちやすくなるため、共感や好意が生まれやすく、問い合わせにもつながりやすくなります。
②コンテンツとして資産になる
ルームツアー動画は、一度作れば終わりではなく、長期的に価値を生み出し続ける「資産」です。
チラシなどの紙媒体は一度配布するとその瞬間で役割を終えますが、
動画は
• 数年前の投稿が今も見られている
• 本数を増やすほど効果が加速する
といった、積み重ね型の集客効果が期待できます。
長く活躍する「コンテンツ資産」として、会社の認知・信頼・問い合わせ獲得に貢献します。
③検討初期の顧客にもアプローチできる
現在、住宅購入の情報収集はSNSやYouTubeといったオンライン中心へと移行しています。
すでに住宅展示場へ来場しているお客様は「ほぼ検討を終えた後」の段階であることが多く、本当の勝負は“もっと前”、つまり検討初期にあります。
ルームツアー動画は、
• 家づくりを意識しはじめたばかりのユーザー
• SNSや動画で「なんとなく情報収集」している層
こうした検討初期の潜在顧客にアプローチできる数少ない手段です。
だからこそ、動画を継続的に発信する意義は大きく、集客効率を大きく左右します。
伸びない理由
動画の構成や尺がバラバラだと、視聴者はすぐ離脱する
YouTubeで動画の評価を左右するのが、「視聴維持率」です。
これは視聴者がどれだけ長く動画を見続けたかを示す指標で、維持率が高いほどYouTubeのアルゴリズムに評価され、多くの人におすすめ表示されやすくなります。
特に重要なのが、動画の構成です。
中でもカギになるのは、最初の15秒。
ここで視聴者の心をつかめなければ、どれだけ内容が良くても離脱されてしまいます。
住宅業界のルームツアー動画では、以下のような情報を冒頭でしっかり伝えるのがポイントです。
• 誰のための家なのか(家族構成)
• どんな想いで設計されたのか(設計意図)
• 素材や仕上がりのこだわり
こうしたストーリー性をもたせることで、「この動画は見る価値がある」と感じてもらいやすくなります。また、オープニングは短く・シンプルにまとめるのが鉄則。テンポよく価値を伝えることで、最後まで視聴される確率が大きく変わります。
何を伝えるか以上に、どう構成するかが大切です。
再生回数が伸びている動画の多くは、
導入 → 見どころ紹介 → 各部屋案内 → まとめ
といった視聴者の興味を引き続ける構成になっています。
一方で、導入が長すぎたり話が前後していたりすると、視聴者はすぐに離脱してしまう傾向にあります。
構成の工夫こそ、再生回数アップの第一歩。ルームツアー動画を伸ばすには、「どこを見せ、どう伝えるか」を戦略的に考えることが重要です。
魅力のないサムネイル・タイトルでは、見られる前に終わる
ルームツアー動画の再生回数が伸びない原因のひとつが、サムネイルやタイトルに魅力がないことです。
YouTubeで動画を選ぶ際、視聴者が最初に目にするのはサムネイル。スマホやPCの画面を見れば分かる通り、画面の大部分を占めているのがサムネイルであり、その印象が「見る・見ない」を左右します。
どれだけ素晴らしい住宅を紹介していても、「ただの写真+物件名」ではクリックされません。
今は「良い家」ではなく、「気になる家」に見せる工夫が必要です。
魅力的なサムネイルをつくるには、
・コピーライティングスキル
・マーケティングスキル
・デザインスキル
・撮影スキル
といった複数の要素が求められます。一見シンプルな作業に見えて、実は非常に高度なクリエイティブワークです。
また、タイトルも重要です。
視聴者の興味や悩みに刺さる具体的な言葉で、「見たい」と思わせることができなければ、スルーされてしまいます。
2020年ごろまでは、ルームツアー動画を出すだけである程度の再生回数が見込めました。
しかし今は競合が多く、「見る価値がなければ別の動画が選ばれる」時代です。
動画の中身より前に、まずは「クリックしてもらう工夫」がなければ、そもそも見てもらえません。
サムネイルとタイトルは、再生回数を左右する“入口”そのもの。
視聴者にとっての「最初の接点」にこそ、もっとも力を入れるべきなのです。
【関連記事】
工務店のYouTubeサムネイルで差をつける!NG例と成功の秘訣を解説
【すぐに実践】動画のタイトルには2つのパターンがあります!
投稿頻度・タイミングがバラバラでは、視聴者に届かない
ルームツアー動画の再生回数が伸びない理由のひとつに、投稿の頻度とタイミングが安定していないことがあります。
YouTubeは、「継続的な配信」や「定期的な更新」を重視するプラットフォームです。
なぜ「投稿頻度」が重要なのか?
• 投稿が月1回や不定期だと、視聴者の習慣にならない
• アルゴリズム上、アクティブなチャンネルの方が表示されやすい
• ファンを育てられず、視聴数も蓄積されにくい
たとえば、毎週●曜日に更新されることが分かっていれば、視聴者は「次も見よう」と期待を持ってチャンネルを訪れるようになります。これはテレビの番組と同じ原理です。
タイミングも戦略的に!
平日の昼間よりも、夜や週末の方が視聴者のアクティブ率が高い傾向にあります。
また、地域やターゲット層(30代の子育て世代など)に合わせて、生活時間に沿った公開時間を選ぶことが大切です。
特に家づくりを検討している層は、土日や夜の時間に情報収集をする傾向があります
つまり、思いつきでアップするのではなく、「誰に・いつ届けるか」を考えて投稿することが、再生回数を伸ばすためのカギになります。
投稿の“質”だけでなく、タイミングと頻度も重要
どれだけ丁寧に作ったルームツアー動画でも、投稿のタイミングや頻度が不規則では、視聴者に届きにくくなります。
「たまたま見かけた」だけで終わってしまう動画にならないように、定期的な発信が不可欠です。
一方で、住宅の性能ばかりを伝える動画も伸びづらい傾向があります。
断熱性や耐久性といった数値的な魅力だけでは、他社との違いが伝わりづらく、視聴者の印象にも残りません。
そこで重要なのが、暮らしのイメージを届ける動画です。
「このリビングでどんな休日が過ごせるか」「ホームシアターを楽しむ生活」など、視聴者が“その家で暮らす自分”を想像できる構成が、問い合わせへとつながります。
また、出演者のストーリー性も大きなポイントです。
たとえば、設計士が家づくりへの想いやこだわりを語り、MCが質問を投げかける形にすると、動画に人間味と信頼感が加わり、視聴者の関心を引きつけます。
投稿は週1回などリズムよく続けることで、チャンネルへの親近感や習慣性が高まります。
特に金曜夜〜日曜にかけての時間帯は、家づくり検討層が動画を見やすいタイミング。このゴールデンタイムを逃さず、“見てもらえる環境”を自ら整えることが再生回数アップの近道です。
伸ばすための工夫と活用法
【関連記事】【2024年最新版】住宅YouTubeでルームツアー動画の成功事例を3つ紹介します
最初の15秒で“見る理由”を与える
YouTubeのアルゴリズムが重視するのが、視聴維持率。
これは「視聴者がどれだけ長く動画を見続けたか」を示す指標で、維持率が高い動画はYouTubeに評価され、より多くの人に表示されるようになります。
その中でも特に重要なのが、“最初の15秒”。
住宅系ルームツアーでは、この冒頭で視聴者の関心を引けなければ即スキップ。
「この動画は自分に関係ある」と思わせる工夫が必要不可欠です。
〈改善のポイント〉
• オープニングは短くテンポよく構成する
• 家族構成・暮らしの背景・設計の意図を早めに紹介する
• 素材のこだわりや施主の声などを冒頭に入れる
こうした構成にすることで、以下のような好循環が生まれます。
• 最後まで見てくれる視聴者が増える
• チャンネル全体の評価が上がる
• 再生回数や登録者数が自然と伸びやすくなる
つまり、「なぜこの動画を見るべきなのか」を最初の15秒で明確に伝えることが、
“再生数が伸びるか・伸びないか”の分かれ道になるのです。
ターゲットを明確にすることが“再生数以上の成果”を生む
どれだけ再生回数が伸びても、見てほしい相手=ターゲットに届かなければ、
問い合わせや反響にはつながりません。
そのため、動画制作の最重要ポイントが「ターゲット設定」です。
〈ターゲット像の描き方〉
• 「女性」ではなく、
→ 「子育て中の30代女性」
→ 「子育てを終えた50代夫婦」など、
家族構成や生活スタイルまで具体的に設定しましょう。
ターゲットが明確になることで、
動画の語り口や見せたいポイントがぶれずに伝わるようになります。
〈ペルソナ設定のコツ〉
• 自社で運用する場合:住まい方・ライフスタイルまで細かく想定
• 外注する場合:住宅選びの悩みや希望などをしっかり伝える
→ 制作側が共感を生む動画を作りやすくなります。
30歳前後の世代は、YouTubeを日常的に活用している層であり、視覚的な訴求力やテンポのよい動画に敏感です。
この層に向けて暮らしをリアルに感じられるコンテンツを届けることで、自然な集客や問い合わせが生まれます。
もちろん、YouTubeは幅広い世代が利用しているため、ターゲットを絞り込んだ動画でも、他層に波及する可能性も大いにあります。再生回数よりも、「誰に見せたいか」を明確にすること。それが、工務店YouTube活用の“反響につながる第一歩”です。
タイトルとサムネイルで“見られる動画”に変える
YouTubeで多くの視聴者に届けるためには、サムネイルとタイトルの工夫が不可欠です。
クリックされなければ、どんなに中身が良くても再生されません。
タイトルのポイント
タイトルは、次の3点が一目でわかる構成にしましょう。
• 誰向けか
• どんな価値があるか
• どんな課題が解決できるか
たとえば、
【プロ監修】新築ルームツアー完全解説
ビフォーアフターでわかる!築古物件リフォーム術
のように、具体性+ベネフィットをしっかり打ち出すことで、検索にも強く、クリック率も上がります。
サムネイルのポイント
サムネイルは動画の第一印象を決める重要な要素。
特に住宅業界では、視覚的なインパクトがカギとなります。
• 現場写真やビフォーアフターの画像
• スタッフの顔写真
• 目立つ数字やキャッチコピー
これらを活用し、「この動画、見てみたい!」と思わせるデザインを心がけましょう。
〈改善策と効果〉
• 改善策: 外観写真を多用し、文字は短く・魅力的に
• 効果: 視聴者の関心を引き、クリック率の向上につながる
ポイントを意識して成功した事例
C社では、サムネイルに
「〇〇万円で実現!」「施工主インタビュー」など具体的で目を引くコピーを加えた結果、
→クリック率が約2倍に向上。
→再生数・問い合わせも大幅にアップしました。
“動画の内容”以前に、“クリックされるかどうか”が成果の分かれ道。
まずは、タイトルとサムネイルで心をつかむことが最優先です。
ストーリー構成で視聴者の共感をつかむ
再生回数が伸びている住宅系ユーチューバーの動画には、「住む人のストーリー」がしっかりと組み込まれています。
ただ単に部屋数や設備を紹介するだけでは、視聴者の記憶に残りません。
具体的には、以下のようなリアルな背景や暮らしぶりが語られることが重要です。
• 家族構成
• なぜこの家を建てたのか
• 設計や素材のこだわり
• 住んでみてどう感じたか
これにより、視聴者は「自分だったらこんな暮らしができるかも…」と想像しながら動画を見られます。
視聴者が本当に知りたいのは、「この家に住んだら、どんな暮らしができるのか?」ということ。そのため、建物自体よりも「人」や「暮らし」にフォーカスした動画が、共感を集めやすく最後まで見られやすいのです。
「家紹介」から「暮らし紹介」へ視点を変えるだけで、再生回数が大きく変わる可能性があります。
動画制作の効率化と品質安定に“テンプレート化”を活用する
ルームツアー動画を継続的に伸ばすためには、制作の効率化と品質の安定が欠かせません。そのために効果的なのが、動画の構成や撮影パターンをテンプレート化することです。
〈テンプレート化のメリット〉
• 制作時間の短縮
毎回ゼロから企画・構成を考える必要がなくなり、効率よく動画が作れます。
• 品質の安定
良い構成や編集パターンを型として使うことで、動画ごとのバラつきを減らせます。
• 視聴者の安心感・リピート率向上
フォーマットが定まると視聴者も見やすくなり、次回も期待してもらいやすくなります。
〈テンプレートに盛り込むべき要素例〉
• 冒頭の挨拶や自己紹介
• 家族構成や設計意図の紹介パート
• こだわりポイントや素材紹介の映像
• 住み心地や生活シーンのインタビュー
• エンディングのまとめと問い合わせ誘導
テンプレート化を進める際は、定期的に効果測定を行い、視聴者の反応を反映しながらアップデートすることが重要です。
これにより、効率的かつ魅力的な動画を安定して提供し、再生回数や問い合わせの増加につなげることができます。
テンプレート化は、動画制作の負担を軽減しながらも、視聴者に魅力的なコンテンツを届け続ける“成功の秘訣と言えるでしょう。
出演者の魅力が視聴者の信頼と共感を生む
住宅会社を選ぶ際、多くの視聴者が重視するのは、「担当者との相性」や「会社の雰囲気」といった感情的な要素です。だからこそ、動画に出演者を登場させて、「どんな人が家づくりを担当しているのか」を伝えることが非常に重要です。
〈出演者の選び方〉
• 知識と経験が豊富な営業担当や設計士、経営者が最適
• 家づくりへのこだわりや思いをしっかり語れる人を選びましょう
• 新入社員など知識不足で説得力に欠ける人の出演は避けるのが無難です
〈出演者が消極的な場合の対処法〉
• 動画の構成や質問内容を丁寧にサポートし、
• 出演のハードルを下げてあげることが大切です
出演者の魅力的な語り口や人柄が、視聴者の信頼と共感を生み、結果的に問い合わせや契約につながる重要なカギとなります。
視聴後の“次の一歩”を促す導線設計が重要
動画を最後まで見てもらった後、視聴者に自然と次の行動を促す導線設計が、
問い合わせや集客アップにつながる大きなポイントです。
〈導線設計のポイント〉
• 動画の最後に問い合わせ先や公式サイトの案内を必ず入れる
• 関連動画や再生リストへの誘導を設置し、チャンネル内での回遊を促す
• 視聴者が迷わず行動できるシンプルな案内を心がける
〈効果的な具体例〉
• 「この家の詳細は概要欄のリンクからご覧ください」
• 「もっと知りたい方はチャンネル登録と高評価をお願いします」
• 「こちらの動画もぜひチェックしてください」と関連動画を紹介
こうした明確な次のアクションを示すことで、視聴者の反応率や滞在時間が向上し、
YouTubeアルゴリズムからの評価も高まります。
結果的に、再生回数アップや問い合わせ増加に直結する導線づくりが必須です。
動画を見た視聴者が迷わず次のステップに進めるよう、導線設計にこだわりましょう。
成功事例から学ぶ!効果的なルームツアー動画活用法

実際にルームツアー動画を活用して成果を上げている工務店の成功事例は、効果的な動画運用のヒントが詰まっています。
〈成功事例のポイント〉
• ターゲットを明確に絞り込んだ動画作りで、視聴者の共感を獲得
• 最初の15秒で興味を引く構成を徹底し、視聴維持率を向上
• スタッフや設計士の出演で信頼感アップを実現
• サムネイルやタイトルに工夫を凝らしクリック率を大幅改善
• 定期的な投稿でチャンネルの認知度とファンを増やす
〈実際の成果例〉
• ある工務店では、動画のクリック率が約2倍に増加し、
• 問い合わせ数が前年比で30%以上アップしたケースもあります。
• また、視聴者からの「家づくりの参考になった」という声も多く、信頼構築に成功しています。
成功事例からわかるのは、動画はただ作るだけでなく、計画的にターゲットや構成を設計し、継続的に改善していくことが重要だということ。これらを踏まえ、貴社の動画戦略にもぜひ成功事例のエッセンスを取り入れてみてください。
問い合わせへの導線

動画内で自然に“見学予約”へ誘導する工夫
営業マンが実際にお客様を案内するように、家の説明をする動画をリール形式で投稿するのも効果的です。
• どんな営業マンが対応するのか
• どんな雰囲気で案内してくれるのか
を視聴者に伝えることで、自社で家づくりを検討しているお客様に安心感を与え、信頼を築くことができます。
このような動画は、契約につながる大きな要因にもなるため、ぜひリール投稿に取り入れてみましょう。動画内で見学予約や問い合わせへの導線を自然に設けることで、視聴者の行動を促しやすくなります。
概要欄・コメント欄を活用した効果的な問い合わせ導線
動画の概要欄やコメント欄は、視聴者が次のアクションを起こすための重要な導線です。ここに問い合わせ先や予約ページのリンクを分かりやすく掲載することが必須となります。
概要欄とコメント欄を効果的に使い分けることで、視聴者の問い合わせハードルを下げ、成約率アップにつなげましょう。
概要欄活用のポイント
• 問い合わせフォームや見学予約ページのURLを必ず記載
• 連絡先電話番号やメールアドレスも明記して信頼感アップ
• 動画のポイントや補足説明も簡潔にまとめると閲覧率向上
コメント欄活用のポイント
• 固定コメントで問い合わせや予約への誘導メッセージを設置
• 視聴者からの質問に積極的に返信し、双方向コミュニケーションを図る
• コメント欄を活用することで、視聴者の興味を逃さず継続的な関係構築が可能に
SNS連携で工務店集客を加速させる
2025年以降、YouTubeだけでなくInstagram、TikTok、LINE公式アカウントなど複数のSNSを融合活用することが工務店集客の大きな武器になります。
〈効果的なSNS連携の具体例〉
• YouTubeで公開した動画をInstagramリールやTikTokショート動画に二次活用
• LINE公式アカウントで動画告知や相談チャットに誘導し、見込み客との接点を多重に持つ
〈B社の成功事例〉
• YouTubeのルームツアー動画公開後、Instagramで編集版ショート動画を配信
• LINE公式では「動画視聴者限定の相談受付」を実施
→ これにより、動画経由の資料請求やイベント申込が前年対比1.7倍に増加
ホームページやSNSアカウントへの誘導も必須
• YouTube概要欄やコメントにホームページやSNSのリンクを掲載し、複数導線から問い合わせや資料請求へ誘導
• YouTube公開に合わせ、ホームページ特設ページやInstagramで情報発信し相互流入を促進
• SNSではダイジェスト版や撮影裏側、スタッフの日常などYouTubeとは異なるコンテンツで別層へアプローチ
YouTube単体ではなく、HP・SNS・MEOを連携させたクロスメディア戦略が成功のカギとなります。
LINE公式アカウント活用例
• 「友だち追加で限定動画プレゼント」
• 「質問・相談ができるチャット窓口」
→ YouTubeからの流入ユーザーを見込み客として囲い込む施策が効果的
複数チャネル連携を強化した工務店では、月間問い合わせ件数が従来比1.5倍以上に増加する具体的な成果も出ています。
問い合わせへのハードルを下げる工夫で反応率アップ
視聴者が動画を見て問い合わせに踏み切るには、ハードルをできるだけ低くする工夫が不可欠です。
〈ハードルを下げる具体的なポイント〉
• 簡単で分かりやすい問い合わせ方法の提示
→ フォームは入力項目を最小限に、電話やLINEチャットなど複数の選択肢を用意する
• 問い合わせの目的を明確にし、「気軽に相談OK」を伝える
→ 「まずは相談だけでも大歓迎」「強引な営業はしません」など安心感を与える文言を添える
• 動画や概要欄で問い合わせメリットをアピール
→ 「無料プラン相談」「来場特典あり」など具体的なメリットを提示して動機付け
〈ユーザー心理に寄り添った導線設計〉
• 視聴者が迷わず問い合わせボタンやリンクにたどり着けるよう、
動画内の案内や概要欄・コメント欄で繰り返し誘導を行う
• 問い合わせ後の対応スピードや丁寧さも重要で、
迅速かつ親身なレスポンスで安心感を強化する
こうした問い合わせのハードルを下げる工夫を積み重ねることで、反応率の向上と問い合わせ増加につながります。
まとめ
ルームツアー動画は、ただ投稿するだけでは効果を発揮しにくい時代です。撮影構成やサムネイルの工夫、SNSやLINE公式との連携、問い合わせのハードルを下げる設計など、「伸ばす仕組み」と「次のアクションにつなげる導線」が成功のカギとなります。
今回ご紹介したような施策をひとつずつ実践することで、視聴回数だけでなく資料請求・来場予約・ファンの獲得といった確かな成果が見えてきます。自社の強みを最大限に活かしたルームツアー戦略を、ぜひ一度見直してみてください。
>>住宅業界・工務店のSNS活用・YouTube運営のお問合せはこちら
「住宅業界のYoutube 運用の教科書」を無料でダウンロード!
\ こんな方におすすめです! /
・ルームツアー動画が集客に繋がらない
・Youtubeを試したがやり方があってるか分からない
・クリック率や再生時間の目安を知りたい
・0からYoutube活用を学びたい