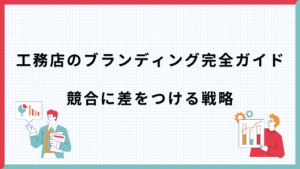【絶対に知って】住宅YouTubeでやってしまいがちな失敗談とは? – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=aBlp5wkhiZg
「住宅業界のYoutube 運用の教科書」を無料でダウンロード!
\ こんな方におすすめです! /
・ルームツアー動画が集客に繋がらない
・Youtubeを試したがやり方があってるか分からない
・クリック率や再生時間の目安を知りたい
・0からYoutube活用を学びたい
住宅業界でYouTubeを活用する企業が増える中、思ったような成果が出ずに悩むケースも少なくありません。
本記事では、住宅業界のYouTube運用でよくある失敗事例を具体的に紹介し、なぜ失敗するのか、その原因を探ります。さらに、失敗から脱却し成果を出すための「改善への7ステップ」も解説しますので、ぜひチェックしてみてください。
これからYouTube運用を始める方、また運用を見直したい方にとって役立つ内容となっています。最後までご覧ください。
>>住宅業界・工務店のSNS活用・YouTube運営のお問合せはこちら
住宅業界YouTubeでよくある失敗10選を紹介
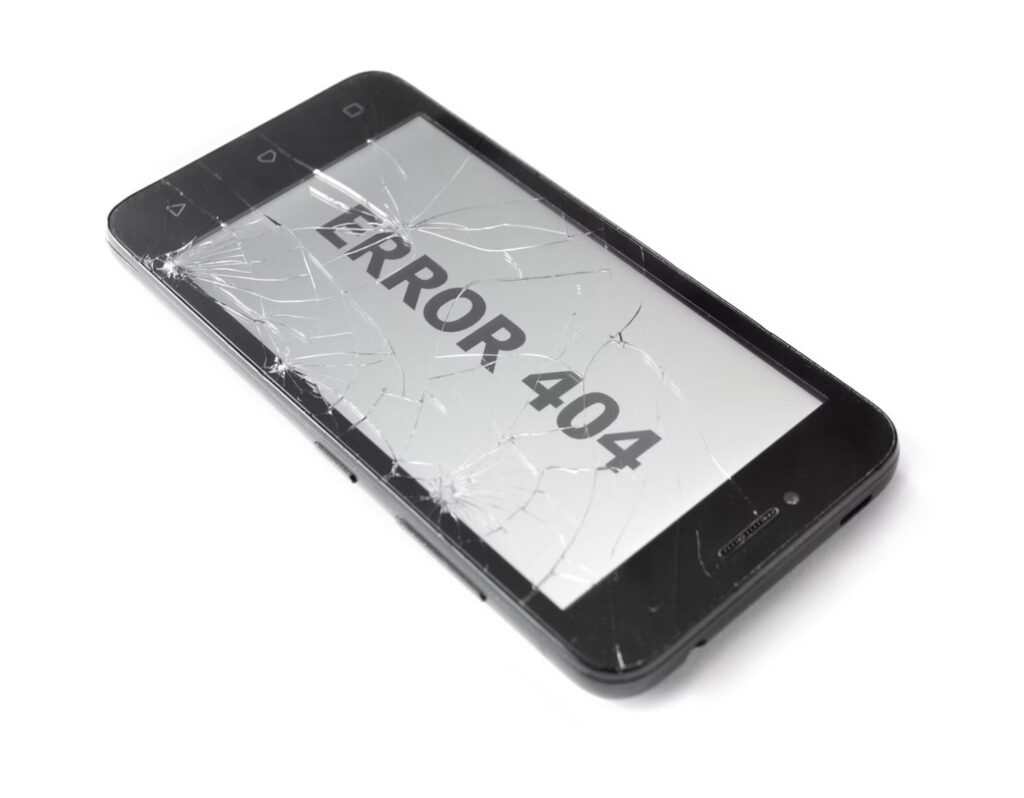
よくある失敗①:会社紹介・社員インタビューから始めてしまう
最初に重視すべきは、「家を買いたい人」に向けた情報発信です。
まだ会社のことを知らない視聴者に対して、いきなり会社紹介や社員インタビューの動画を出しても、関心を引きにくく、再生数も伸びづらい傾向にあります。
視聴者がまず求めているのは、
「この会社はどんな家を建ててくれるのか?」
「自分の理想が実現できるのか?」
といった、住宅そのものに関する具体的な情報です。
この段階で「誰が働いているか」を伝えても、視聴者にとってはまだ他人事。
まずはルームツアーや間取りの工夫、家づくりの進め方など、住まいに直結するテーマを優先的に発信することが、関心を引き、信頼につながる第一歩になります。
よくある失敗②:社員に登録や視聴を促してしまう
ついやってしまいがちなのが、社員にYouTubeチャンネルの登録や視聴をお願いしてしまうこと。
一見すると応援のように見えますが、これはYouTubeのアルゴリズムに悪影響を及ぼす可能性があります。
YouTubeは、視聴者の興味・関心に基づいて動画を推薦する仕組みです。
しかし、社員が登録・視聴すると、アルゴリズムが「この動画は社内向けのもの」と認識してしまい、本来届けたい“家を探しているユーザー”におすすめされにくくなるリスクがあります。
また、社員が業務以外で視聴しているジャンル(音楽、料理、スポーツなど)の影響で、住宅関連動画が視聴者層に正しく届かなくなるケースも。
数字を伸ばすには、本当に届けたい相手=家を買いたい人に向けた最適な配信設計が必要です。社内の応援より、ユーザー目線のアルゴリズム設計を優先しましょう。
よくある失敗③:導線設計がない
YouTube動画を作ることに集中しすぎて、視聴後の動線設計が抜けてしまうのはよくあるミスです。動画はあくまで集客の入り口。その先に、どう行動してもらうかを明確にする必要があります。
理想的なのは、視聴後に自社サイトやランディングページ(LP)へ誘導し、見学会や無料相談への申し込みへつなげる導線を用意すること。たとえば、動画の概要欄やコメント欄にリンクを貼る、動画内で案内を入れるなどが有効です。
この導線がないと、視聴者は動画を見ただけで離脱してしまい、せっかくの興味が「問い合わせ」や「来場」につながりません。
YouTube運用を成果に結びつけるためには、「見てもらったあと、どう行動してほしいか?」を明確にした設計が欠かせません。
よくある失敗④:広告を先行しすぎる
再生回数を増やすために広告を使うのは、一見効果的に見えます。
しかし、広告からの流入はまだ住宅購入に本気で興味を持っていない層に届きやすいため、最初の段階では避けるべきです。
関心度の低い視聴者が多いと、YouTubeのアルゴリズムは動画の評価を下げ、「良い動画」として認められにくくなってしまいます。
そのため、チャンネルが一定の視聴者を獲得し、基盤ができてから広告を活用するほうが効果的です。まずは自然流入を増やし、ファン層を育ててから広告を使うことが成功のポイントとなります。
よくある失敗⑤:目的のわからない企画を作ってしまう
住宅業界のYouTubeコンテンツの目的は、視聴者に住宅購入を促すことにあります。
ところが、再生回数や認知度ばかりを意識するあまり、ターゲット層に無関係なダンス動画や社員の自己紹介など、エンタメ要素に偏った企画を作ってしまうことがあります。
視聴者が本当に求めているのは、家を購入するための具体的で役立つ情報です。
そのため、企画を考える際には、目的を見失わず、住宅購入検討者のニーズに沿った内容に絞ることが重要です。
無目的な企画は視聴者の興味を引けず、結果としてチャンネルの信頼度や成約率を下げてしまうリスクがあります。
よくある失敗⑥:ショート動画ばかり投稿して情報不足になる
YouTubeのショート動画はリーチを広げるのに効果的ですが、住宅購入の決断にはより深く具体的な情報提供が必要です。
短い1分程度の動画だけでは、視聴者が家を購入しようと本気で考えるための十分な情報を伝えることは難しいのが現実です。
住宅購入は大きな決断のため、視聴者は間取りの工夫や素材の特徴、費用の内訳など、詳しく納得できる情報を求めています。
そのため、ショート動画に加え、長尺の動画で視聴者のニーズに合った内容をしっかり伝えることが重要です。
これにより、視聴者の信頼を獲得し、問い合わせや見学予約などの具体的なアクションにつなげることができます。
よくある失敗⑦:過度なエンタメに走ってしまう
YouTubeでダンスやユーモアなどのエンタメ要素を取り入れることは、一見魅力的に映ります。
しかし、住宅業界のコンテンツにおいては、過度なエンタメは視聴者を引き込むことが難しくなる場合が多いです。
住宅購入を検討している視聴者は、信頼できる情報を求めており、真面目に住宅情報を伝える動画に安心感を持ちます。
結果として、信頼感のあるコンテンツのほうが、視聴者の共感を得て問い合わせや来場につながりやすくなります。
エンタメ要素はバランスを見て適切に取り入れつつ、住宅の専門性や誠実さをしっかり伝えることが成功のポイントです。
よくある失敗⑧:競合分析をしない
競合他社のYouTubeチャンネルを参考にすることは、非常に有効な戦略です。
どのような動画が人気を集めているのか、どのような表現方法が効果的なのかを学ぶことで、自社の動画制作にも活かせます。
しかし、競合の動向を無視すると、独自のアイデアや新しいアプローチが出てこず、コンテンツがマンネリ化するリスクがあります。
常に市場を観察し、成功事例を参考にしながら、改善や工夫を繰り返すことが成長の鍵です。
【関連記事】【意外と簡単?】工務店YouTubeの競合チャンネルの分析方法をご紹介! |工務店マーケティング |内製化支援
よくある失敗⑨:YouTubeアルゴリズムの理解不足
YouTubeのアルゴリズムを理解せずに運用を進めることは、成果につながりません。
YouTubeは、視聴維持率やクリック率、再生時間といったデータをもとに動画を推薦しています。
そのため、これらの指標を意識したコンテンツ制作が不可欠です。
どの動画がよく再生され、どの動画が視聴されにくいのかをデータとして把握し、改善を続けることが成功のポイントとなります。
よくある失敗⑩:分析と改善をしない
YouTube運用においては、分析と改善の繰り返しが成果を生み出すカギです。
どのコンテンツが効果的だったのかを視聴者の反応からしっかり分析し、その結果を次回の動画制作に活かしましょう。
再生回数だけでなく、視聴維持率やエンゲージメント(コメントや高評価など)も重要な指標です。
また、改善の際には映像のクオリティや音声の調整、カット割りなどの細かい部分にも注意を払うことが、視聴者の満足度向上につながります。
これらを意識せずに運用を続けると、成長が停滞しやすいため、定期的な振り返りと改善を習慣化することが大切です。
やりがちな失敗事例5選
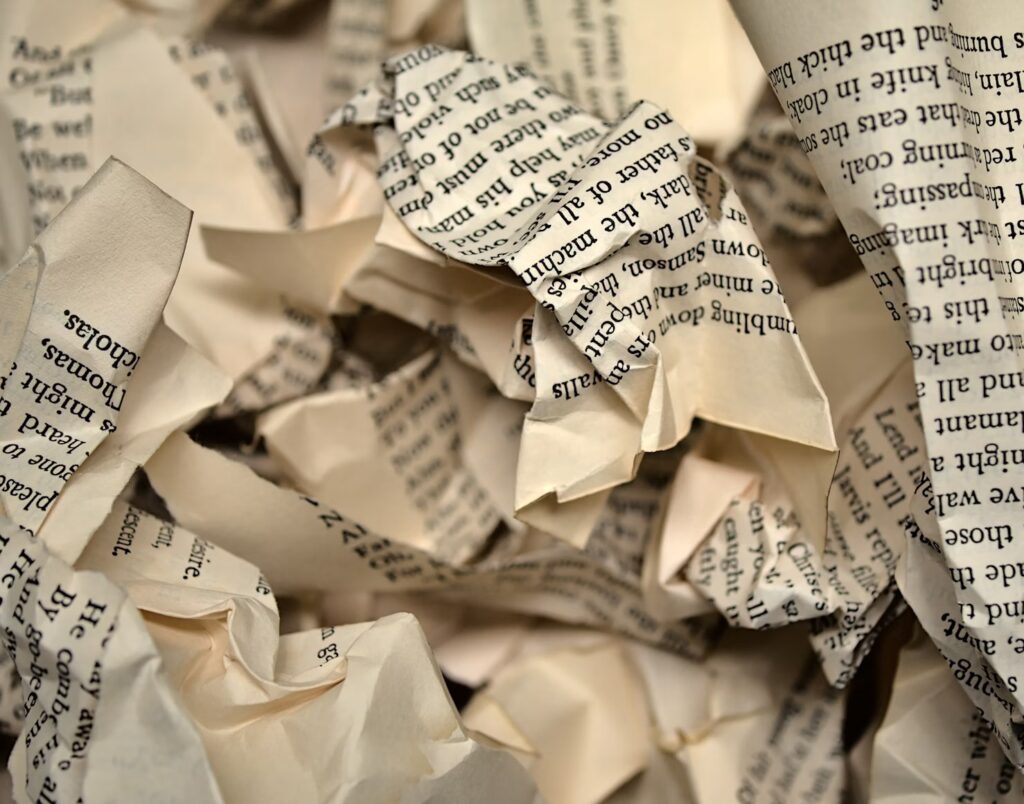
単調なコンテンツばかりになる
住宅業界のYouTube運用でよくある失敗の一つが、同じような内容や形式の動画ばかり投稿してしまうことです。
例えば、ルームツアーや施工事例だけに偏ってしまうと、視聴者が飽きやすく、チャンネル全体の魅力が薄れてしまいます。
視聴者の興味を引き続けるためには、複数の企画やテーマを組み合わせることが大切です。
間取りのポイント、住宅ローンの解説、実際の住み心地の声、よくある質問への回答など、幅広い内容を取り入れることで、飽きられず継続的に見てもらいやすくなります。
単調なコンテンツを繰り返すと、視聴者の離脱率が高まり、チャンネルの成長が鈍化する原因にもなります。
多様な切り口で住宅にまつわる情報を届ける工夫をしましょう。
不定期投稿でファンがつかない
YouTube運用で意外と多い失敗が、動画を不定期に投稿してしまうことです。
闇雲に毎日投稿するのも問題ですが、逆に投稿のタイミングがバラバラで一定しないと、視聴者が「いつ見ればいいのかわからない」となり、ファンをつくりにくくなります。
重要なのは、動画の配信日時を決めて一定のリズムで投稿することです。
たとえば、毎週土曜日の19時といった決まった日時にアップすれば、視聴者は「この時間を楽しみに待とう」となり、固定のファンが増えやすくなります。
特にYouTubeは週末に視聴が増える傾向があるため、週末の配信がおすすめです。
固定のファンを作ることは、単なる登録者数以上にチャンネルの成功に重要な要素です。
質を保ちながら、計画的な配信スケジュールを立てることがYouTube運用の成果を左右します。
新人だけの出演では信頼感が薄くなる
新人社員だけが動画に出演するケースは、親しみやすさはあるものの、視聴者に信頼感を与えにくいという課題があります。
住宅購入は大きな決断のため、視聴者は経験豊富なスタッフや専門家の意見も求めています。
新人だけの出演に偏ると、情報の深みや説得力が不足し、視聴者が不安を感じてしまうことも。
ベテラン社員や設計士、施工管理者など、様々な立場の社員がバランスよく登場することで、信頼感を高めることができます。
視聴者が安心して問い合わせや相談に進めるよう、出演メンバーの多様化を意識しましょう。
完璧主義すぎて動画投稿が遅れる
動画のクオリティを追求するあまり、完成度にこだわりすぎて投稿が遅れてしまうことはよくある失敗です。
完璧な動画を目指す気持ちは大切ですが、YouTubeは継続的な投稿とスピード感も重要な要素です。
完璧を求めすぎると、投稿頻度が落ちて視聴者の関心が薄れてしまい、チャンネルの成長が停滞する原因になります。
また、細部にこだわりすぎて制作コストがかかりすぎる場合もあります。
まずはある程度のクオリティを確保しつつ、継続して動画を投稿することが最優先。
視聴者の反応を見ながら、徐々に改善を重ねていく姿勢が成果につながります。
社員だけで動画をシェアしてしまう
社員同士で動画をシェアすることは一見良い応援になりますが、視聴者拡大にはほとんど効果がありません。社員の視聴は視聴履歴に影響し、YouTubeのアルゴリズムが住宅購入を検討する顧客層に動画を届けにくくなるリスクもあります。
動画の拡散を狙うなら、本当に家を検討しているユーザーや見込み客に届く工夫が必要です。SNS広告や地域の情報サイトへの掲載、口コミを促すなど、ターゲット層にリーチする方法を取り入れましょう。
社員によるシェアだけに頼らず、戦略的な視聴者獲得を意識することがチャンネル成長の鍵です。
【関連記事】工務店の集客戦略!SNSの効果的な使い方と失敗しない運用ポイント
成功の3大要素

成功の3大要素①:尖ったコンセプトで差別化する
YouTubeで成功するためには、他社と明確に差別化できる尖ったコンセプトを持つことが不可欠です。
住宅業界は競争が激しく、似たような動画が多く存在します。その中で視聴者の目を引きつけるには、独自の視点や強みを前面に打ち出す必要があります。
例えば、「自然素材にこだわった家づくり」や「家づくりの裏側を赤裸々に公開」など、特定のテーマに特化したコンテンツは視聴者の興味を引きやすくなります。
尖ったコンセプトがあることで、ファンが付きやすく、長期的なチャンネル成長につながります。
成功の3大要素②:明確なターゲットを設定する
YouTubeで成果を出すためには、誰に向けて発信するのかを明確にすることが重要です。ターゲットがはっきりしていないと、メッセージがぼやけてしまい、視聴者の共感を得にくくなります。
例えば、「30代の子育て世代向け」や「二世帯住宅を検討しているファミリー」など、具体的なターゲット像を設定しましょう。これにより、視聴者が「自分のための情報だ」と感じやすくなり、動画の効果が高まります。
明確なターゲットを持つことで、コンテンツの内容や表現方法もブレずに作成でき、チャンネルのブランディングにもつながります。
成功の3大要素③:高いコミットメントで継続する
YouTubeで結果を出すには、高いコミットメントを持って継続的に運用を続けることが不可欠です。
動画投稿や改善作業は一朝一夕で成果が出るものではなく、根気強く取り組む姿勢が求められます。
定期的な動画アップや分析、改善を怠らず続けることで、徐々に視聴者との信頼関係が築かれ、チャンネルの成長につながります。途中で諦めずに、長期的な視点で取り組むことが成功への近道です。
改善への7ステップ
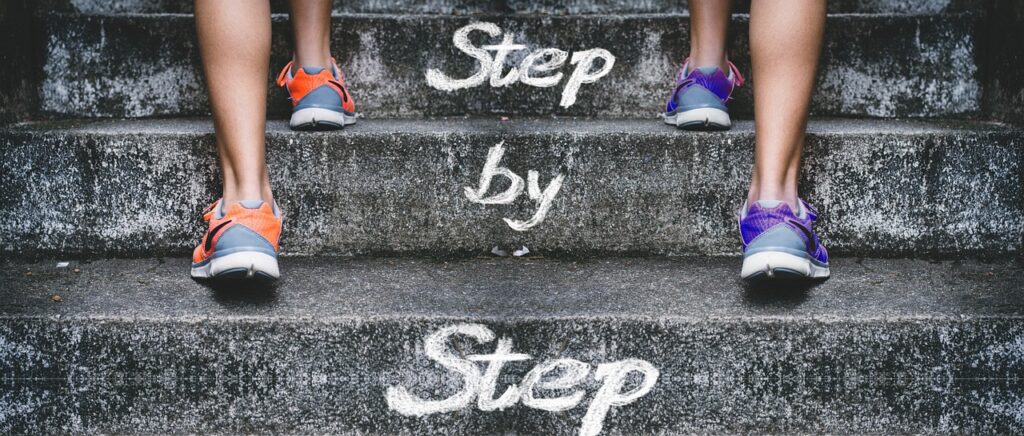
改善へのステップ①:ペルソナを明確に設定する
動画制作の改善を始めるにあたり、まずは具体的なペルソナ(理想の視聴者像)を設定することが重要です。ペルソナを明確にすることで、誰に向けて何を伝えるべきかがはっきりし、内容のブレを防げます。
例えば、「30代の共働き夫婦で、子育て中のマイホーム購入検討者」といった具体的な人物像を描き、ニーズや悩みを想像しましょう。
こうしたペルソナ設定により、動画のテーマや言葉遣い、伝え方を最適化でき、視聴者の共感や関心を引きやすくなります。
改善へのステップ②:明確な目的を設定する
動画改善を効果的に進めるには、まず明確な目的を設定することが欠かせません。
「認知度向上」「見学会への集客」「問い合わせ増加」など、具体的なゴールを決めることで、動画の内容や訴求ポイントがぶれずに作成できます。
目的が曖昧だと、視聴者に何を伝えたいのか伝わりづらくなり、効果も限定的になります。
目的に沿った指標を設定し、改善の成果をしっかりと測ることが成功の鍵です。
改善へのステップ③:視聴者を次の行動に導く導線を作る
動画を見た視聴者が次に何をすればよいか迷わないよう、明確な導線を設計することが重要です。たとえば、動画の最後や概要欄でウェブサイトやランディングページへの誘導を促し、見学会や無料相談への申し込みにつなげましょう。
適切な導線がなければ、興味を持った視聴者も次のステップに進まず、成果につながりにくくなります。視聴者の行動を自然に促す導線設計は、YouTube運用の効果を最大化するための必須ポイントです。
改善へのステップ④:動画のクオリティを高める
視聴者の満足度を高めるためには、映像や音声のクオリティをしっかり向上させることが重要です。
画質や音質が悪いと、内容が良くても視聴者の離脱を招く原因になります。
照明やカメラアングル、マイクの使い方に気を配り、見やすく聞き取りやすい動画を目指しましょう。また、無駄なカットを減らしてテンポよく編集することも、視聴維持率アップにつながります。
一定以上のクオリティを保つことで、チャンネルの信頼性が向上し、視聴者からの評価も高まります。
改善へのステップ⑤:企画の幅を広げる
動画の内容が単調になると、視聴者の興味を維持しづらくなります。
そのため、複数の企画やテーマを取り入れて、バリエーション豊かなコンテンツを提供することが重要です。
例えば、施工事例の紹介だけでなく、住宅ローンの解説、スタッフインタビュー、よくある質問への回答など、様々な角度から住宅に関する情報を届けましょう。
企画の幅を広げることで、異なるニーズを持つ視聴者層にもリーチしやすくなります。
多様なコンテンツは視聴者の飽きを防ぎ、チャンネルの成長にもつながるポイントです。
改善へのステップ⑥:データを分析して改善を繰り返す
YouTube運用では、視聴データを細かく分析し、改善を継続することが成果につながる重要なポイントです。
再生回数や視聴維持率、クリック率などの指標を確認し、どの動画が視聴者に支持されているかを把握しましょう。
分析した結果をもとに、動画の内容や構成、配信時間などを調整し、より効果的なコンテンツ作りを目指します。
このPDCAサイクルを回し続けることで、徐々にチャンネルの成長が加速します。
改善へのステップ⑦:継続して取り組むことが成功の鍵
YouTubeで成果を出すには、一度きりで終わらず、継続して動画制作と改善に取り組むことが不可欠です。短期間で結果が出ないことも多いため、根気強く続ける姿勢が重要になります。
定期的な投稿スケジュールを守りながら、分析・改善を繰り返すことで、視聴者との信頼関係を築き、チャンネルの成長を促進します。諦めずにコツコツと継続することが、YouTube成功への最短ルートです。
まとめ
住宅業界のYouTube運用では、失敗を避けるためのポイントを押さえることが成功への第一歩です。今回紹介した失敗事例と改善のステップを参考に、ターゲット設定やコンテンツ企画、分析・改善を地道に積み重ねていきましょう。
継続的な取り組みと高いコミットメントがあれば、YouTubeは強力な集客・ブランディングツールとなります。ぜひ本記事を活用して、住宅業界でのYouTube運用を成功に導いてください。
>>住宅業界・工務店のSNS活用・YouTube運営のお問合せはこちら
「住宅業界のYoutube 運用の教科書」を無料でダウンロード!
\ こんな方におすすめです! /
・ルームツアー動画が集客に繋がらない
・Youtubeを試したがやり方があってるか分からない
・クリック率や再生時間の目安を知りたい
・0からYoutube活用を学びたい