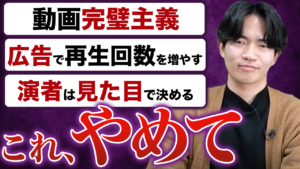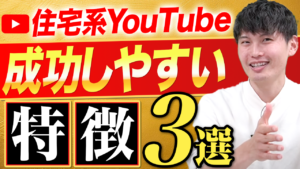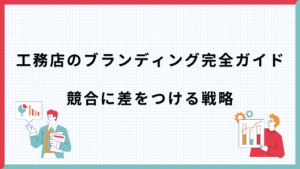【あなたは大丈夫?】住宅会社がYouTubeでやってはいけない考え方 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=UM8NFjS2TCI
「住宅業界のYoutube 運用の教科書」を無料でダウンロード!
\ こんな方におすすめです! /
・ルームツアー動画が集客に繋がらない
・Youtubeを試したがやり方があってるか分からない
・クリック率や再生時間の目安を知りたい
・0からYoutube活用を学びたい
住宅業界におけるYouTube運用は、集客やブランド力向上に大きな可能性を秘めています。しかし、目的やターゲットを明確にせず運用を始めてしまうと、思った成果が得られない落とし穴が数多く存在します。
本記事では、住宅会社が陥りやすい6つの落とし穴を整理し、それぞれの回避法や成功事例を交えて解説します。YouTube運用を効率的に行い、問い合わせや契約につなげたい工務店・住宅会社の方必見です。
>>住宅業界・工務店のSNS活用・YouTube運営のお問合せはこちら
住宅業界のYouTube運用で陥りやすい6つの落とし穴

登録者数だけを追い求める運用は危険!
YouTube運用の初期段階で陥りがちなのが、「登録者数=成功」という考え方です。もちろん数字が伸びるのは嬉しいことですが、住宅業界・工務店の最終目的は「家を売ること」。
たとえ登録者数が少なくても、深く刺さるコンテンツを届けられれば、お問い合わせや成約につながるケースは多くあります。
そのためには、視聴維持率・コメント数・リピート率などのエンゲージメント指標を重視し、数字の見せかけに惑わされない運用が重要です。
再生回数だけで動画の良し悪しを判断しない!
再生回数は気になる指標ですが、これだけに一喜一憂するのは危険です。たとえ再生数が少なくても、クリック率や視聴完了率が高ければ効果的な動画といえます。
また、「可愛い社員さん」や「派手な演出」で再生数を稼ぐことは可能ですが、これは本来の目的である「家を売る」には直結しません。
大切なのは、見た目の数字よりも見込み客の心をつかむコンテンツを作ることです。
ルームツアー1本足打法は危険!
工務店の人気コンテンツといえばルームツアー動画ですが、これだけでは家の購入に直結しにくいのが現実です。展示会での初回見学のように、ルームツアーはあくまで「入口」に過ぎません。
購入につなげるためには、
• 知識系コンテンツ(家づくりのポイント解説)
• お客様インタビュー(実際の満足度や体験談)
• 大工さん密着動画(施工の安心感を伝える)
など、共感や信頼を生むコンテンツを組み合わせることが重要です。
さらに、モデルハウスがない場合や施主様の許可が取れない場合に備えて、過去のお施主様から撮影許可をもらい素材を確保しておくと、安定的な配信が可能になります。
演者を出さない無機質な動画は損!
会社の雰囲気や人柄を伝えるには、演者の登場が効果的です。
社員が出演することで視聴者に親しみを持ってもらいやすくなり、「この人と話してみたい」という感情が生まれ、問い合わせにつながる可能性が高まります。
MCや外部タレントではなく、会社のリアルな顔を見せることで、信頼感とブランドの一貫性を築きましょう。
【関連記事】【完全ガイド】住宅系YouTubeで差がつく!演者問題をズバッと解決
面白さ重視で方向性がブレるのは危険!
視聴者を楽しませようとする姿勢は大切ですが、無理な演出や不自然なキャラ作りは逆効果です。住宅業界のYouTube視聴者は、家づくりに関する真剣な情報を求めているケースが多いため、自然体の魅力を伝えることが重要です。
普段の性格や雰囲気を、少しだけわかりやすく表現する程度で十分。無理に笑いを取りに行くよりも、誠実さや共感を優先しましょう。
YouTubeだけに依存する運用は集客効率を下げる!
YouTubeはあくまでマーケティングツールの一つであり、単体では契約までつながりにくいのが現実です。最大限の効果を出すには、ホームページやInstagram、LINEなど他媒体との連携が不可欠です。
例えば、YouTubeで興味を持った視聴者が訪れるホームページが古く更新もされていないと、その場で熱が冷めてしまう可能性があります。一方、Instagramで施工事例や日常の発信を続ければ、視聴者との関係を深めリピーター化も期待できます。
YouTubeは集客の入り口にすぎません。他媒体との動線設計を行い、反響を最大化しましょう。
YouTube運用での失敗事例

目的やターゲットが曖昧なまま運用を始めてしまう失敗
YouTube運用でよくあるのが、「とりあえず始めてみよう」と目的やターゲットを明確にせずにスタートしてしまうケースです。この状態では、動画の内容や方向性がブレやすく、視聴者にもメッセージが伝わりにくくなります。
住宅業界の場合、誰に・何を・どのように伝えるかを事前に決めることが重要です。
たとえば「30代の子育て世代に、省エネ住宅の魅力をわかりやすく伝える」といった具体的な設定を行えば、動画のテーマや演出も一貫し、効果的な集客につながります。
更新頻度がバラバラで視聴者が離れてしまう失敗
動画の更新頻度が不定期だと、視聴者の期待感が薄れ、チャンネル離れを招く原因になります。特に住宅業界では、家づくりを検討している期間が限られているため、情報発信のタイミングを逃すと見込み客を取りこぼしてしまいます。
理想は、週1回や隔週など継続できるペースを決めて運用すること。更新予定を固定化すれば、視聴者が「次も見よう」と思いやすくなり、チャンネルの信頼性も高まります。
分析と改善を怠って同じ失敗を繰り返すケース
動画を投稿しても、再生回数や視聴維持率、コメント反応などを分析しないまま運用を続けると、改善点が見えず成果が伸び悩みます。原因を特定しないまま新しい動画を作っても、同じミスを繰り返すだけです。
改善のポイントは、データを数値で把握し、次の企画や編集に反映させること。例えば、離脱率が高い場面を短くする、反応が良かった企画をシリーズ化するなど、PDCAを回すことでチャンネルの成長スピードが加速します。
回避法

数より質を意識した見込み客獲得
YouTube運用では、再生回数やチャンネル登録者数だけを追うのは危険です。数字が伸びても、自社の商材やサービスに興味のない視聴者ばかりでは契約にはつながりません。
重要なのは、自社のターゲット像に合った視聴者層を集めること。そのためには、企画段階で「どんな悩みを持つ人に届けたいか」を明確にし、内容・タイトル・サムネイルをその層に最適化することが欠かせません。
こうすることで、数は少なくても契約や問い合わせにつながる“質の高い見込み客”を安定的に獲得できます。
視聴者の共感を呼ぶテーマ選びで差をつける
地域密着型の工務店がYouTubeで成果を出すには、地元ならではのニーズに寄り添ったテーマ選びが重要です。
ただ「ルームツアーを撮る」だけでは埋もれてしまう時代。企画力こそ運用の明暗を分けます。
〈地域密着ならではのテーマが共感を生むポイント〉
• 地元の視聴者が“自分ごと”として感じられるテーマは、再生回数や問い合わせに直結
• タイトルに地域名を入れるとSEO効果も期待できる
〈企画例と内容のポイント〉
• 〇〇市で人気の間取りベスト3:地域名を入れてSEO強化
• この地域に合った断熱・耐震の話:気候・土地特性を活かして専門性と信頼感UP
• 地域のイベントレポート:親近感を与え、共感・認知の獲得につながる
• 家づくりの基礎知識:「耐震の違い」「予算別の間取り」など実用情報を提供
• 社長・スタッフの想い:温かみや親しみを伝え、安心感を構築
• OB宅訪問:実際に住む家の様子を紹介し、信頼の証を示す
こうしたテーマ設定を行うことで、地域のターゲットに刺さるコンテンツを作り、集客・信頼構築につなげられます。
ルームツアー+αで差別化するコンテンツ戦略
工務店のYouTube活用で人気のルームツアー動画は、玄関から入り、間取りや収納をナレーション付きで紹介するのが基本です。ユーザーの注目度が高く、多くの工務店が活用しています。
しかし、ルームツアーだけでは限界があります。集客効果を高めるには、+αの情報や工夫を加えることが重要です。
〈具体的な+αの工夫例〉
• 周辺環境や店舗情報の紹介:家の内装だけでなく地域情報も伝える
• スタッフのコメントや施工ポイントの解説:信頼感や専門性をアピール
• 物件に興味のある人向けの詳細情報:内見動画として具体的に役立つ内容を提供
• ブログやSNSと連動:じっくり見てもらえる導線を作る
これにより、単なるルームツアーを超えた価値ある情報提供型コンテンツとなり、契約や問い合わせにつながる可能性が高まります。
【関連記事】【2024年最新版】住宅YouTubeでルームツアー動画の成功事例を3つ紹介します
スタッフの顔を出して親近感・信頼感を高める
YouTubeは、工務店がお客様との信頼関係を深める強力なツールです。自社の技術力や施工ノウハウを動画でわかりやすく解説することで、視聴者に「この会社は信頼できる」と感じてもらいやすくなります。
さらに、スタッフや職人の顔や人柄を見せることで安心感がアップ。自らの言葉で仕事への想いを語ることで、親近感や心理的な壁を下げ、信頼度を高めます。
こうした動画を継続的に配信することで、自然と「信用できる工務店」というブランド力が確立され、視聴者が問い合わせや契約を検討するきっかけにつながります。
共感を生むストーリー性で視聴者を引き込む
工務店のYouTube運用では、単なる情報提供だけでなくストーリー性を持たせることが重要です。施工事例やお客様の家づくりの過程を、始まり→課題→解決→完成といった流れで見せることで、視聴者は自然と感情移入できます。
ストーリーを意識することで、
• 家づくりの魅力や会社の強みが伝わりやすくなる
• 視聴者の共感を得て、問い合わせや契約につながりやすくなる
社員や施主の声を交えた物語形式の動画は、情報の伝わり方も格段に向上し、信頼感やブランド力の向上にも効果的です。
YouTubeだけで完結せずSNS・HPと連携して反響を最大化
YouTube単体では、集客や反響効果が限定的になりがちです。Instagram、TikTok、LINE、ホームページなどと連携した導線設計を行うことで、初めてWeb全体で成果を生む運用が可能になります。
具体的には、
• ショート動画で施工のビフォーアフターを紹介:短時間で興味を引き、拡散も期待できる
• 職人の技術や施工ノウハウを短く紹介:専門性や信頼感をアピール
• SNS上でのコメント・シェア対応:視聴者との関係を深め、認知度向上
このように、YouTubeを軸にSNSやHPを連動させる戦略を構築することで、幅広いターゲット層にリーチでき、集客や採用活動など多方面での効果を最大化できます。
【関連記事】工務店の集客戦略!SNSの効果的な使い方と失敗しない運用ポイント
PDCA運用で改善を繰り返しチャンネルを成長させる
YouTube運用で成果を出すには、投稿して終わりではなく、分析・改善を繰り返すPDCA運用が欠かせません。再生回数や視聴維持率、クリック率などのデータをもとに、何が効果的で何が改善点かを明確にします。
具体的には、
• 離脱率が高い場面を短く編集する
• 反応の良い企画をシリーズ化して継続配信
• サムネイルやタイトルの改善でクリック率向上
こうした改善を定期的に行うことで、チャンネル全体の視聴体験が向上し、問い合わせや契約につながる可能性も高まります。PDCA運用は、YouTube運用を戦略的に進めるための基本かつ最も重要なステップです。
YouTube運用成功へのセルフチェックリスト

登録者数・再生回数だけに偏っていないかチェック
YouTube運用でよく注目される登録者数や再生回数ですが、これだけに偏るのは危険です。数値が多くても、ターゲットとなる見込み客に刺さっていなければ意味がありません。
セルフチェックのポイントは、
• 登録者数や再生回数だけで満足していないか
• クリック率や視聴維持率、コメント数などのエンゲージメント指標も意識しているか
数字の表面だけで判断せず、実際にお問い合わせや契約につながるかを基準に評価することが重要です。
コンテンツの更新頻度は安定しているかチェック
動画の投稿が不定期だと、視聴者の期待感が薄れ、チャンネル離れを招く原因になります。特に住宅業界では、家づくりを検討するタイミングが限られているため、情報発信のタイミングを逃すと見込み客を取りこぼす可能性があります。
セルフチェックのポイントは、
• 投稿ペースが週1回や隔週など継続可能なリズムになっているか
• 更新予定が明確で視聴者に予測可能か
安定した更新を行うことで、視聴者に「次も見よう」と思わせる信頼感を与え、チャンネルの成長につなげることができます
他媒体との連動はできているかチェック
YouTube単体での運用だけでは、集客効果が限定的になりがちです。Instagram、TikTok、LINE、ホームページなど他媒体と連携した導線設計ができているかを確認しましょう。
セルフチェックのポイントは、
• 投稿した動画がブログやSNSで紹介されているか
• 視聴者がYouTubeからホームページやLINEにスムーズに移動できる導線があるか
• ショート動画やSNS投稿を活用して、幅広いターゲット層にリーチできているか
他媒体との連動を意識することで、YouTube動画の情報が単なる閲覧に終わらず、問い合わせや契約につながる導線を作ることが可能です。
効果検証を定期的に行っているかチェック
動画を投稿したら、再生回数や視聴維持率、クリック率、コメント数などのデータをもとに効果を検証していますか?分析せずに運用を続けると、改善点が見えず、同じ失敗を繰り返す原因になります。
セルフチェックのポイントは、
• データを定期的に確認しているか
• 離脱ポイントや反応の良い企画を分析して改善しているか
• 次回の動画制作やタイトル・サムネイルにフィードバックを反映しているか
こうしたPDCAサイクルを回すことで、チャンネル全体の視聴体験が向上し、問い合わせや契約につながる可能性を高められます。
成功事例
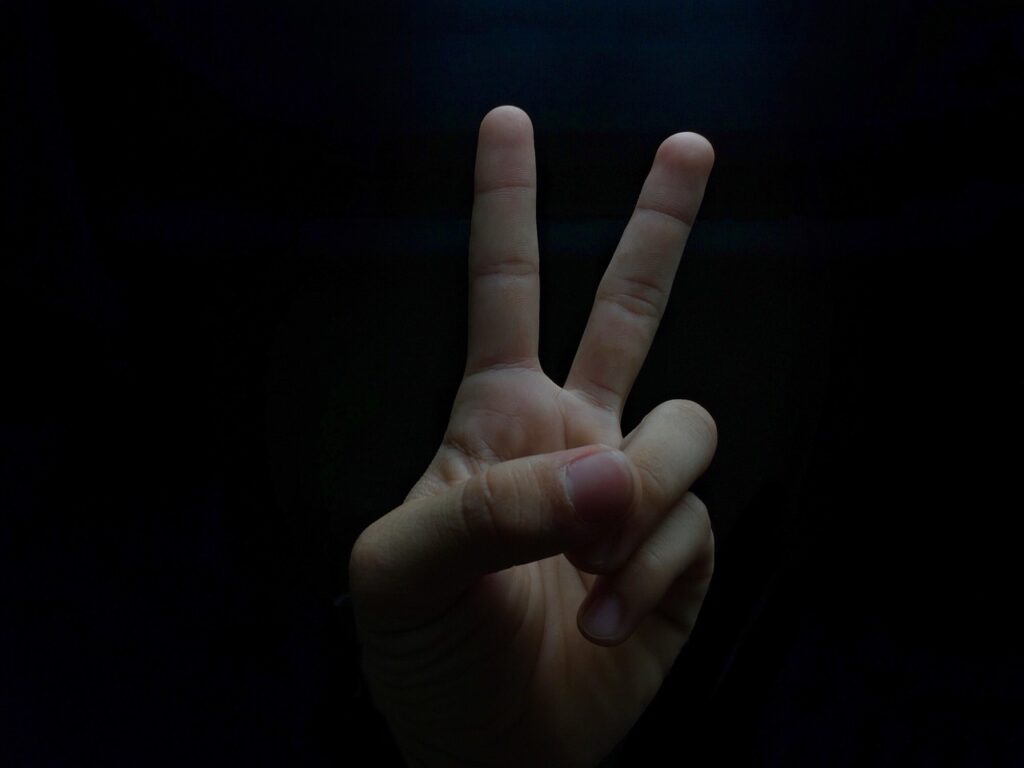
スタッフ出演で問い合わせ率が3倍に
工務店のYouTube成功事例として、スタッフ出演動画が効果を上げています。社員や職人が自らの言葉で仕事への想いや施工のこだわりを語ることで、視聴者に親近感や信頼感を与えられます。
結果として、動画を見た視聴者が「この会社に相談してみたい」と感じ、問い合わせ率や資料請求数が大幅に向上するケースもあります。顔が見えることで会社の雰囲気も伝わり、単なる情報提供では得られないブランド価値の向上にもつながります。
シリーズ化でリピーターを増やす
工務店のYouTube成功事例では、テーマをシリーズ化することで視聴者の継続視聴を促しています。
たとえば「施工のビフォーアフター」「家づくりの基礎知識」「スタッフ密着」など、テーマごとに複数回の動画を順番に配信することで、視聴者は次回もチェックしたくなります。
シリーズ化のメリットは、
• 視聴者のチャンネル滞在時間やリピート率が向上
• 企画が定着することでブランドや専門性の認知につながる
• 関連動画として他の動画の再生も促進できる
このように、シリーズ展開はチャンネルのファン化と問い合わせ増加に大きく貢献します。
SNS連携をしてキャンペーン情報の反響を最大化
工務店のYouTube成功事例では、SNSと連動したキャンペーンが効果を発揮しています。動画を公開する際に、InstagramやLINE、TikTokなどのSNSで告知や関連投稿を行うことで、視聴者のリーチと反応率を大幅に向上させることが可能です。
具体例としては、
• YouTubeで公開した施工動画をInstagramのストーリーズやリールで紹介
• 動画内で告知したキャンペーンをSNSで応募受付
• ショート動画やサムネイルで興味を引き、WebサイトやLINEに誘導
こうした連携により、単体の動画だけでは届かない層へのアプローチができ、問い合わせや資料請求の増加にもつながります。
まとめ
住宅業界のYouTube運用には、登録者数や再生回数だけを追ってしまう、ルームツアーに偏る、SNSやHPとの連携が不十分など、さまざまな落とし穴があります。しかし、ターゲットを明確にし、コンテンツにストーリー性や親近感を持たせ、他媒体と連動したPDCA運用を行うことで、これらは回避可能です。
本記事で紹介した回避法や成功事例を参考に、戦略的にYouTubeを活用すれば、住宅会社としての信頼感向上や集客力アップに直結します。
>>住宅業界・工務店のSNS活用・YouTube運営のお問合せはこちら
「住宅業界のYoutube 運用の教科書」を無料でダウンロード!
\ こんな方におすすめです! /
・ルームツアー動画が集客に繋がらない
・Youtubeを試したがやり方があってるか分からない
・クリック率や再生時間の目安を知りたい
・0からYoutube活用を学びたい