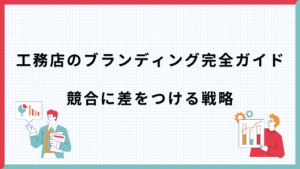【想定外】工務店YouTubeの外注後の落とし穴 【工務店マーケティング】 – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Alfyvqlpdl0
「住宅業界のYoutube 運用の教科書」を無料でダウンロード!
\ こんな方におすすめです! /
・ルームツアー動画が集客に繋がらない
・Youtubeを試したがやり方があってるか分からない
・クリック率や再生時間の目安を知りたい
・0からYoutube活用を学びたい
住宅業界でもYouTubeを活用した集客が一般化する中で、動画制作を「外注すべきか」「自社で対応すべきか」に悩む工務店が増えています。限られた人材や時間の中で、効果的にYouTubeチャンネルを運用するためには、戦略的な外注活用がカギとなります。
本記事では、外注のメリット・デメリットを踏まえつつ、工務店にとって最適なYouTube運用の方法について解説していきます。
>>住宅業界・工務店のSNS活用・YouTube運営のお問合せはこちら
今、工務店にとってのYouTube活用が重要な理由
YouTubeの重要性は、年々高まっています。単なる流行ではなく、「集客・ブランディング・信頼構築」のすべてにおいて、YouTubeが重要な戦略ツールになっているのです。
1. 圧倒的な利用者数と情報拡散力
YouTubeは世界最大級の動画プラットフォームで、毎日数十億人がアクセスしています。
チラシや折込広告では届かなかった層にも、効果的にアプローチできるのが特徴です。
特に2020年以降、動画を活用した集客が主流になりつつあり、やらないこと自体が“機会損失”とまで言われるようになりました。
2. 圧倒的な情報伝達量「動画は文字の5,000倍」
住宅やリノベーションの魅力を、「文章」より「写真」、「写真」より「動画」で伝えるのが現代の常識。
実際に動画は文字の約5,000倍の情報を伝えるとも言われており、完成物の魅力や空気感、職人の仕事ぶりを“体感”として届けることが可能です。
3. 信頼感が生まれる「顔出しの力」
社員や職人の顔が見える動画には、信頼を感じやすいもの。
実際に働くスタッフの声・表情・雰囲気が見えることで、視聴者に「この会社に頼んでみたい」と思わせるきっかけを生みます。
4. 顧客層との親和性が高い
現在の住宅購入層である30代前後は、YouTubeが当たり前の世代。
情報収集に動画を使うのが日常になっており、住宅選びの過程でも自然にYouTube検索をしています。
5. 施工事例や会社の魅力をわかりやすく伝えられる
写真では伝えきれなかった質感・間取り感覚・空気感などを、動画なら直感的に伝えられます。
お施主様とのストーリーを盛り込めば、共感と記憶にも残りやすくなります。
6. コメント欄を通じて、未来のお施主様とつながる
動画を見た視聴者がコメントを通じて質問・相談してくることも多く、見込み客との自然なコミュニケーションが生まれます
7. SEOにも強い
YouTube動画はGoogle検索にも表示されるため、住宅系の検索ワードで上位表示を狙う際にも強力な武器になります。
ホームページと連携することで、Web集客の相乗効果も期待できます。
8. 共感がファンを生み、認知度アップへ
社長の人柄、職人の真摯な仕事ぶり、社員同士の関係性など「人」に共感してくれるファンが生まれやすいのもYouTubeの魅力。
感情に訴えるコンテンツで、地域での認知度も自然と広がっていきます。
9. 他社との差別化を実現
まだまだ「やっていない会社」も多い業界だからこそ、YouTubeに取り組むだけで差別化に直結します。
うまく活用すれば、採用活動にもつなげられる“武器”になります。
なぜ工務店はYouTube運用を外注するのか?プロに任せる理由
YouTubeの重要性は理解していても、「実際には社内で運用できない」という工務店は少なくありません。
そんな中、外注という選択をする工務店が増えている背景には、いくつかの明確な理由があります。
1. 社内に動画編集や運用の知識がない
工務店の本業は「家づくり」。
YouTubeに必要な「撮影機材」「編集スキル」「サムネイル作成」などは専門外で、社内にノウハウを持っている人がいないケースがほとんどです。
2. 時間的リソースが確保できない
現場対応・設計・営業・アフター対応と、日々の業務で手一杯。
動画を1本作るには、企画・撮影・編集・アップロード・分析といった膨大な工数がかかるため、社内で継続するのは現実的に難しいと感じることも。
3. プロ品質の動画でブランディングしたい
スマホで撮っただけの動画では、住宅の魅力やブランド価値が伝わりにくい場合も。
映像や音声、構成が整った“プロ品質の動画”で他社と差別化を図るために、専門業者に依頼する選択をする工務店が増えています。
4. 企画・運用・改善まで一括で任せられる
YouTube運用は「動画を出すだけ」では成果につながりません。
チャンネル設計・タイトルやサムネイルの設計・投稿頻度の管理・数値分析といった、運用の全体設計が必要です。
その部分までワンストップで対応してくれる外注先に依頼することで、継続的な成果を目指せるようになります。
5. SNS全体の戦略と連動できる
YouTube単体ではなく、Instagram・TikTok・公式サイトとの連携が求められる中で、外注先のマーケティング会社ならSNS全体の戦略提案が可能。
YouTubeを軸にしたSNS戦略を構築するために、外注する工務店が増加しています。
工務店YouTubeを外注するメリット・デメリット
YouTube運用を外注することで、手間を減らしつつ高品質な動画を発信できる一方で、注意しておきたい落とし穴も存在します。
ここでは、外注の「メリット」と「デメリット」を比較しながら、検討の参考になるように整理していきます。
〈外注のメリット〉
①高品質な動画が作れる
プロの手によって撮影・編集されるため、見た目の印象やブランド力が格段にアップします。
②時間の確保ができる
社員が動画に時間を取られず、本業に集中できます。
③継続的な配信が可能になる
外注先スケジュールを管理してくれるため、更新が止まるリスクが減ります。
④最新トレンドを活用できる
プロはYouTubeのアルゴリズムや視聴者傾向を熟知しており、戦略的な運用が可能です。
⑤SNS全体の連携も期待できる
YouTubeだけでなく、InstagramやTikTokとの連動施策も提案してくれる外注先もあります。
〈外注のデメリット〉
①費用がかかる
撮影・編集・運用管理まで依頼すると、月額数万円〜数十万円の費用が発生します。
②社内の“らしさ”がでにくい
企画や演出によっては、工務店の空気感や職人の温かみが伝わりにくいこともあります。
③内容の確認に時間がかかる
撮影や編集の都合、チェックや修正が必要になる場合があり、コミュニケーションコストが発生します。
④外注先によってクオリティに差がある
「とりあえず動画が作れる」だけの業者に依頼すると、意図が伝わらず、満足いく結果が得られない場合があります。
工務店がYouTube動画制作の外注時に陥りがちな5つの落とし穴
外注によってYouTube運用の負担は軽減されますが、任せきりにすることで起こる「想定外のトラブル」も少なくありません。
ここでは、工務店がYouTubeを外注したときに直面しがちな落とし穴を5つに分けてご紹介します。
1. ルームツアー撮影ができない
工務店の人気コンテンツといえばルームツアー。しかし、モデルハウスがなかったり、施主様の許可が取れなかったりすると、撮影ができないこともあります。過去のお施主様に撮影許可をもらい、素材を確保しておくようにしておけば、いざという時に安心です。
2. コンテンツ企画が浮かばない
「ルームツアーが無理なら、次は何を撮る?」と手が止まりがちになります。自社の強みやお客様のよくある質問を基に、How to系や豆知識系動画を企画しましょう。撮影前に動画ストックを数本用意しておくと安心です。
3. 改善ができない(アナリティスク未活用)
再生数が伸びないのに、何が悪いのかわからない…という状態に陥ることもあります。YouTubeアナリティクスでインプレッション数・クリック率・視聴維持率を分析し、改善サイクルを回すことが重要です。
4. 社内リソース不足でチェックが追いつかない
動画チェックや内容確認に時間がかけられず、公開が遅れる、内容にズレが出るなどの課題もあります。無理のないスケジュールと役割分担を外注先と共有し、社内リソースに合わせた体制を構築しましょう。
5. YouTubeだけで完結しようとしてしまう
YouTubeは集客の入り口にすぎません。単体では契約まで結びつきにくい傾向にあります。InstagramやLINE、ホームページと連携した動線設計を行うことで、反響を最大化させましょう。
工務店がYouTube外注先を選ぶときの5つのチェックポイント
YouTubeを外注する際、ただ「動画を作れる会社」に依頼するだけでは、思うような成果は得られません。
重要なのは、“自社の目的や雰囲気に合ったパートナーを選ぶこと”。ここでは、工務店が外注先を選ぶ際の重要ポイントを5つにまとめました。
1. 住宅・建築業界に理解があるか
住宅業界の専門性を理解していない外注先では、住宅の魅せ方や専門用語の扱い方がズレることも。
施工中の映像や現場の温度感などを正確に表現できるかしっかり確認しましょう。
2. コンテンツ企画から関われるか
「ただ編集だけ」「言われたものを形にするだけ」では、成果につながりません。強みを引き出す企画提案力がある会社かどうかを確認しましょう。また、ターゲットや市場に合わせた企画戦略を立ててくれるかがカギです。
3. 分析と改善提案まで行ってくれるか
YouTubeは「出して終わり」ではなく、反応を見て改善していくメディアです。
投稿後のアナリティクス分析や改善提案まで含めて対応できる会社を選びましょう。
さらに、再生数や視聴維持率などをもとにした、具体的な改善案が出せるかが重要です。
4. 社内のリソースと連携できるか
外注とはいえ、社内とのやり取りは必須です。担当者とのコミュニケーションがスムーズかも重要なチェックポイントになります。
社内の確認フローやスケジュールに柔軟に対応してくれるか?もしっかりチェックさいておきましょう。
5. SNS・Webなど他媒体との連携提案があるか
YouTube単体では効果が薄い場合が多いです。Instagram、LINE、ホームページなどを含めた導線設計の知見があるかを確認しましょう。「YouTubeを軸に、Web全体で反響を生む」視点を持っている会社が理想です。
運用の成功法則
運用を成功に導くカギは「企画とテーマ選び」にあり
地域密着型の工務店がYouTubeで成果を出すには、“地元ならでは”のニーズに寄り添ったテーマ選びが重要です。
ただ「ルームツアーを撮る」だけでは埋もれてしまう時代。企画力こそが、YouTube運用の明暗を分けます。
◆ 地域密着ならではのテーマが共感を生む
地元の視聴者が“自分ごと”として感じられるテーマが、再生回数や問合せに直結します
| 地元ニーズを反映した企画例 | 内容のポイント |
| 〇〇市で人気の間取りベスト3 | 実際の地域名をタイトルに入れるとSEO効果も抜群 |
| この地域に合った断熱・耐震の話 | 気候・土地特性を生かした専門知識で信頼感UP |
| 地域のイベントレポート | 地元の人に親近感を与え、共感・認知の獲得につながる |
◆ 実際に成果を出している事例(B社)
• 「○○市限定の土地情報」「地域の施工例」など、ピンポイントなテーマで投稿
• 地域イベントの様子を動画で発信し、地元住民の共感と親近感を獲得
→ 結果として、動画経由の問い合わせ件数が前年比2倍超に
◆ ジャンル別:おすすめ動画企画10選
①ルームツアー(月1)
内容:【10〜15分】設計士が見どころを3つ紹介
ポイント:予約フォームを概要欄に掲載
②家づくり講座(週1ショート)
内容:【60秒】検索ワードをタイトルに
ポイント:初心者向け解説でSEOに強い
③施工インタビュー
内容:【5〜8分】リアルな声+ハイライト編集で信頼感&背中押し
④ビフォーアフター動画
内容:リノベ案件に効果的
ポイント:Before→CGプラン→完成までを物語型に構成
⑤アフターメンテ講座
内容:OB施主向け
ポイント:QRで配布すると間合せ削減に効果的
⑥スタッフ紹介(縦動画)
内容:【60秒】採用にも活用
ポイント:趣味→想い→得意分野の順で構成
⑦社員座談会
内容:「ZEH vs パッシブ」など専門性とカルチャーを伝える
⑧コラボ企画
内容:地元YouTuberやDIY職人と組んで認知拡大
ポイント:相互リンクで登録者増
⑨密着ドキュメンタリー
内容:上棟日・職人の1日に密着
ポイント:情熱が伝わりファン化に直結
⑩イベントLIVE配信
内容:県政見学会を30分ライブ→チャプター付きアイカーブで資産化
◆ その他の有効テーマ
• 家づくりの基礎知識:「耐震って実際どう違う?」「予算別の間取りの違い」など
• 社長・スタッフの想い:温かみや親しみが伝わり、安心感に繋がる
• OB宅訪問:実際に住んでいる家の様子を紹介=信頼の証
運用を成功に導く「制作の工夫」
YouTubeで集客効果を高めるには、「ルームツアー」や「施工事例紹介」といった動画の企画・構成に工夫が必要です。完成物件や実際に暮らしているお客様のお宅を紹介することで、紙の資料や写真では伝えきれない“空間の広さ”や“住み心地”をリアルに感じてもらうことができます。
タイトルに具体性を
たとえば、「2LDK・狭小住宅ルームツアー」や「築30年の家が最新リフォームでこう変わる」など、ユーザーの悩みに刺さる具体的なタイトルをつけると、クリック率が大幅に向上します。
動線を意識した撮影構成
案内の順番は「玄関 → リビング → キッチン → 水回り」といった実際の生活導線に沿って進めるのがおすすめです。要所でこだわりの設計や設備の解説を加えることで、視聴者の理解と満足度が深まります。さらに、ビフォーアフターの比較映像を挿入することで、変化のインパクトを強調できます。
「人」が伝わる動画で信頼感アップ
小規模工務店の最大の強みは“人の魅力”です。社長やスタッフ、職人自身が動画に登場して、仕事のこだわりや家づくりへの想いを語ることで、視聴者との心理的距離が縮まり、信頼感につながります。
実際に、社員が週替わりで出演する動画を配信しているC社では、「職人さんの顔が見えるから安心」「会社の雰囲気が伝わって親しみが持てる」といった反響が多く、問い合わせや成約に結びついています。
継続する仕組みをつくる
運用が続かなくなる原因として多いのが、「ネタ切れ」や「担当者の負担増」です。これを防ぐには、最初から完璧を目指すのではなく、無理のない投稿ペースを設け、社内全体で取り組む体制を整えることが大切です。
たとえばB社では、
• 月2本ペースでスタート
• 企画は全員で持ち寄る
• まとめ撮影・編集で負担軽減
といった工夫を行い、長期運用につなげています。さらに社内SNSや定例ミーティングで成果を共有することで、スタッフのモチベーションも維持されています。
成功のポイントは「小さな継続」
特別な機材や予算がなくても、工夫次第で成果につながる動画制作は可能です。最初は地道でも、小さな成功体験を積み重ねていくことが、継続的な成果とブランディングに直結します。
運用を成功させるには「改善」の仕組みがカギ
YouTubeを始めたばかりの頃は、なかなか成果が見えづらいもの。しかし、最初から完璧な運用を目指すのではなく、「投稿を続けながら改善していく」という意識を持つことが成功への第一歩です。
再生回数や離脱ポイントを定期的にチェック
まず意識したいのが、動画ごとの数値チェックです。再生回数や視聴維持率、どこで視聴者が離脱しているかなど、YouTubeアナリティクスのデータを活用しましょう。
たとえば、動画の冒頭で離脱が多い場合は「導入トークが長い」「興味を引くカットが足りない」などの可能性があります。タイトルやサムネイルと中身にズレがあるケースも要注意です。
視聴者のコメントや反応に耳を傾ける
コメント欄やアンケート機能、SNS上の反応からも、多くのヒントが得られます。「もっと◯◯を見たい」「テンポが遅い」など、視聴者からの声は改善の宝庫。毎回チェックして、次の動画に活かすことが大切です。
改善→実践→検証のサイクルをつくる
改善は1回で終わりではなく、小さく検証を重ねるPDCA(Plan→Do→Check→Act)の考え方が重要です。
例えば:
• 1ヶ月に1回は数値を振り返る時間をつくる
• 新しい編集や構成に挑戦し、反応を比較
• うまくいった点・失敗した点を社内で共有
こうした習慣が、運用の精度を少しずつ高めていきます。
「育てる」視点がブランディングにつながる
動画の運用は短距離走ではなく、長距離マラソンです。初めはうまくいかなくても、少しずつ改善を重ねていくことで、ブランドとしての一貫性が生まれ、ファンが増え、結果的に集客や信頼獲得につながります。
地道な改善こそが、YouTube運用を成功に導く最大の武器です。
自社で行うべきYouTube動画制作
撮影・編集の基本と成功のポイント
工務店のYouTube運用では、プロに外注せずとも“伝わる動画”を自社で制作することが可能です。そのためには、撮影と編集の基本を押さえ、社内で無理なく続けられる運用体制をつくることが重要です。
スマホと一眼レフの上手な使い分けがカギ
動画のクオリティは、必ずしも高価な機材で決まるわけではありません。
最新のスマートフォンであれば、4K撮影も可能で、特に屋内ルームツアーやスタッフインタビューなど動きの少ないシーンではスマホで十分対応できます。手軽さとコスト面での強みも大きな魅力です。
一方で、一眼レフやミラーレスカメラは、空間の広がりや光の表現に優れており、「完成物件の外観」「ビフォーアフターの比較」などに適しています。
例えば、物件外観は一眼レフで、インタビューはスマホで撮るなど、シーンごとに機材を使い分けることで映像全体のクオリティが向上します。三脚やジンバルを使えば、どちらの機材でも安定した映像が撮れる点もポイントです。
編集作業は“シンプル&効率的”が成功の近道
撮影後の編集では、「カット編集」「テロップ追加」「BGMの挿入」など、基本的な操作だけでも十分に見やすく仕上げることが可能です。
特に無料で使えるiMovieやCapCutは直感的な操作が可能で、初めての編集にもおすすめ。プロ仕様のPremiere ProやFinal Cut Proも、慣れれば効率化に役立ちます。
テンポ良く見せる編集を心がけ、「共通のオープニング・エンディング動画をテンプレ化」「定型のBGMやテロップをパターン化」することで編集時間を短縮。B社ではこれにより、1本あたりの編集時間を6時間から2時間にまで削減し、毎月3本以上の動画公開を実現しています。
撮影・編集前の準備が完成度を左右する
よくある失敗例として、「音声が聞き取りにくい」「ブレ・ボケがひどい」「編集テンポが悪い」「動画のネタが尽きる」などが挙げられます。
これを防ぐためには、事前準備が不可欠です。
• 外付けマイクで雑音対策
• 窓や照明を意識した明るい撮影環境
• 台本や撮影進行表の作成
• 撮影現場の掃除や整理整頓
また、編集段階では、「不要なシーンは思い切ってカット」「テロップで要点を補足」「BGMの音量バランスに注意」といった細やかな配慮が、視聴者の満足度を大きく左右します。
C社では、毎回視聴者アンケートを取り、視点・構成・音量などへのフィードバックを改善に活用。その積み重ねが、再生数や高評価率の向上につながっています。
自社制作動画の強みとは?工務店だからこそ伝えられるリアルな魅力
工務店が自社でYouTube動画を制作する最大の強みは、何と言っても「現場のリアルな魅力」と「人間味のある情報」を直接伝えられることです。
① 現場の生の声・空気感をそのまま発信できる
職人やスタッフが実際に働く現場の様子、施工のこだわりや工夫を自社制作だからこそ自然体で撮影・紹介できます。外注では伝わりづらい細かなディテールや“働く人の想い”をリアルに伝えることが可能です。
② 顧客目線に寄り添った動画を柔軟に作れる
自社スタッフが制作に携わることで、顧客の疑問や関心を踏まえた企画や内容にすぐ対応できます。お客様の声やよくある質問を動画に反映させるなど、きめ細やかなコンテンツづくりが可能です。
③ スピーディーな動画公開でタイムリーな情報発信が可能
外注に比べて社内で撮影・編集を行うため、急な現場の進捗やイベント情報もタイムリーに動画化できます。旬の話題を逃さず発信できるのは大きなアドバンテージです。
④ コストを抑えながら継続的な発信ができる
高額な外注費をかけずに、スマホや手持ち機材で動画制作が可能なため、コストを抑えて継続的に動画を配信しやすい環境が整います。継続的な発信こそYouTube運用の成功の鍵です。
YouTube動画で築く「お客様との信頼関係」
YouTubeは、工務店がお客様との信頼関係を深める強力なツールです。
専門知識やスキルを直接伝えられます。自社の技術力や施工ノウハウを動画でわかりやすく解説することで、お客様に「この会社は信頼できる」と感じてもらいやすくなります。
スタッフの顔や人柄を見せることで安心感アップ
働くスタッフや職人が動画に出演し、自らの言葉で仕事への想いを語ることで、親近感や安心感を生み出します。顔が見えることで、お客様の心理的な壁が低くなり、信頼度が高まります。
結果として工務店の信用度向上につながります。こうした動画を継続的に配信することで、「信用できる工務店」としてのブランド力が自然に確立されます。
補完ツールとしてのInstagram活用も効果的
YouTubeで信頼関係を築く一方で、Instagramなど他のSNSも併用すれば、より多角的にお客様とつながることができます。動画と写真を組み合わせて使うことで、幅広い層にリーチしやすくなります。
外注と社内制作バランス
それぞれのメリット・デメリットを理解して最適運用
工務店がYouTube集客を始める際、社内制作と外注のどちらにするか悩むケースが多いです。それぞれにメリット・デメリットがあり、自社のリソースや目的に合わせたバランスが重要になります。
社内制作のメリット・デメリット
〈メリット〉
• 現場スタッフや広報担当が直接撮影・編集を担当するため、リアルな現場の空気感や社内の雰囲気を伝えやすい
• 親しみやすさや安心感が視聴者に伝わりやすく、信頼構築に効果的
• コストを抑えられ、日常的な動画更新がしやすい
〈デメリット〉
• 動画編集の経験が浅いとクオリティが安定しにくい
• 担当者の作業負担が増え、時間確保が難しい場合がある
外注活用のメリット・デメリット
〈メリット〉
• プロの技術による高品質な映像制作や編集が期待できる
• 特に「会社紹介」「ルームツアー」など重要な動画をスポットで依頼できる
• 制作効率が上がり、社内の負担を軽減できる
〈デメリット〉
• 1本あたり数万円~数十万円と費用がかかる場合が多い
• 制作スケジュールの調整が必要で、タイムリーな配信が難しいこともある
バランスを取る運用例
A社の事例では、最初の10本を外注で高品質に仕上げ、その後は社内制作へ切り替えました。これにより、コスト削減と制作ノウハウの蓄積を両立し、長期的な安定運用を実現しています。
外注と社内制作のバランスにDX活用を取り入れる重要性
近年、工務店のYouTube運用においては、外注と社内制作のバランスに加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)活用が不可欠となっています。
DXで制作効率と品質向上を実現
動画撮影や編集には専用ツールやクラウドサービスを活用し、社内外の制作チームがスムーズに連携できる環境を整えることが重要です。例えば、オンラインの編集共有プラットフォームを使えば、外注先とのやりとりがスピーディーになり、修正依頼やフィードバックのやり取りが効率化されます。
社内制作の負担軽減と継続的運用の支援
DXツールを導入することで、動画制作のテンプレート管理や自動化が可能になり、初心者でも短時間で質の高い編集ができるようになります。これにより、社内担当者の負担を減らし、継続的な動画発信が安定します。
データ分析による改善サイクルの強化
YouTubeの視聴データやエンゲージメントをデジタルツールで分析し、効果的な動画テーマや編集スタイルを科学的に判断することができます。こうしたデータドリブンな改善が、外注と社内制作双方のクオリティ向上に役立ちます。
外注と社内制作のバランスで考える「動画の役割」理解の重要性
工務店のYouTube動画制作では、外注と社内制作のバランスを考える際に、動画それぞれの役割を明確にすることが成功のポイントです。
代表的な動画は外注で高品質に制作
会社紹介やルームツアーなど、工務店のブランドイメージや信頼感を大きく左右する重要な動画は、外注でプロの技術を活用し、クオリティを重視して制作するのが効果的です。これにより、視聴者に強い印象を与え、集客やブランディングに直結します。
日常的な情報発信は社内制作でスピーディーに対応
一方で、スタッフの紹介、現場の進捗報告、施工のポイント解説など、顧客との距離感を縮めるための親しみやすい動画は社内制作が向いています。迅速に撮影・編集できるため、タイムリーな情報発信や細かなフォローアップが可能です。
役割に応じた使い分けで効果最大化
このように、動画の役割に応じて外注と社内制作を使い分けることで、コストパフォーマンスと動画の質を両立し、効率的なYouTube運用が実現します。
YouTubeの未来
YouTubeの未来を切り開く「AI活用」の可能性
AI技術の進化によって、YouTube運用の現場は大きく変化しています。
編集作業の自動化で効率アップ
「自動編集ツール」「テロップ自動生成」「BGM・音声自動挿入」など、AIを活用したサービスが次々登場。これにより、これまで時間と手間がかかっていた動画編集が劇的に効率化されます。
実例:編集時間の大幅短縮
A社ではAI編集ツールの導入により、動画1本あたりの編集時間を4時間から1時間以内に短縮。これが定期的な投稿やPDCAサイクルの高速化を可能にし、効果的な運用を実現しました。
AIによるテーマ提案やサムネイル自動作成も活用
AIを使ったサムネイル自動生成やYouTubeアナリティクスに基づく動画テーマ自動提案により、最小限の工数で最大限の効果を狙えます。
中小工務店でも手軽に導入可能に
専門知識がなくてもプロ品質の動画制作・運用ができる環境が整い、AIと人のアイデア・地域性を組み合わせた新しい集客スタイルが主流になることが期待されています。
YouTubeの未来における「新しいアプローチ」の重要性
多くの施主様は、工務店やハウスビルダーに相談したりモデルルームを見学したりする前に、自らインターネットで情報収集を行っています。その中で、YouTubeは非常に有力な情報収集ツールの一つとなっているのです。
検討初期段階の顧客と早期に接点を持つ
YouTubeを活用することで、住宅購入検討の初期段階にいるお客様とつながることが可能になり、新規顧客獲得の大きなチャンスとなります。特にルームツアー動画は、具体的な住まいのイメージを視覚的に伝えられるため、この段階の顧客へのアプローチに効果的です。
オフラインからオンラインへの購買行動のシフト
以前は住宅展示場や工務店への直接訪問が主流でしたが、現在はSNSや動画サイト、マッチングサイトなどオンラインでの情報収集が主流に。実際に展示場に足を運んだり問い合わせたりする頃には、多くの顧客が既にある程度の検討を終えていることが一般的です。
Web上での早期接触が集客成功のカギ
このような消費者行動を踏まえると、検討初期の段階でWeb上の情報を活用している顧客にどうアプローチするかが、集客において非常に重要な課題となります。検索エンジンだけでなく、SNSやYouTubeでのルームツアー動画が、その役割を担っています。
結論
YouTube運用は、外注とうまく付き合うことで安定した成果を生み出せます。工務店にとっては、「自社の強みを活かしながら、外注で手間を省く」ことが成功のポイント。適切なパートナー選びと、目的に合わせた使い分けが、効果的なYouTube集客へとつながります。
>>住宅業界・工務店のSNS活用・YouTube運営のお問合せはこちら
「住宅業界のYoutube 運用の教科書」を無料でダウンロード!
\ こんな方におすすめです! /
・ルームツアー動画が集客に繋がらない
・Youtubeを試したがやり方があってるか分からない
・クリック率や再生時間の目安を知りたい
・0からYoutube活用を学びたい